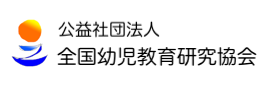投稿者: zenyoken
全幼研教育経営研修会 岩手大会の情報を公開しました
第39回-全幼研教育経営研修会(岩手大会)(2018/11/3(土)開催)のページを公開しました。参加申し込みをお待ちしております。
群馬支部から 全幼研ワクワクプロジェクト開催
西日本の大雨、台風被害に続いて、北海道での大地震と、日本各地に被害が出ているようです。ご親戚等が被害に遭われた皆様には、お見舞い申し上げます。
さて、本日(9月8日)、全幼研ワクワクプロジェクト(群馬)・全幼研群馬支部第1回研修会が、太田市の金山幼稚園で14:00から開催されました。
講師は東京学芸大学の岩立京子先生で、演題は「新しい教育要領・保育所保育指針と保育の実際」でした。岩立先生のお話は、新しい教育要領や指針では、先生の資料の最初に載せてある3枚の写真の意味として、3歳→4歳→5歳と着実に学びを積み上げていくことと、子どもたちの学びが深くなるように子どもの姿の微細なところを丁寧に、そしてしっかりと読み取っていくことが一層求められているというところから始まりました。続いて、今回の改訂について、なぜこのように改訂(改定)されてきたのかという背景をきちんと理解しておくことが必要であるとし、背景についても詳しくご説明いただきました。ハウツーだけで対処していくのではなく、改訂(改定)の必然性を知った上で、やらされるのではなく、先生方が主体的に取り組んでいく(子どもの未来に向けてチャレンジしていく)ことこそが重要であると話されました。
脳科学の発展や追跡調査の結果などから、0・1・2歳を含めた就学前の子どもへの教育の重要性が社会的にも認められるようになってきていることも、これまでの研究結果を示しながら、分かりやすく説明していただきました。また、生活の多様化や体験の不足、いじめの増加(特に小学校低学年)、高校生の自己評価や社会参加意識などの低さなどの子どもたちの実態から、今回の改訂(改定)のポイントへお話をつなげていただきました。
子どもの主体性・能動性を生かす教育が幼児教育(一斉保育のような場面でも、これが幼児教育の本質)であり、そのためには、環境の構成が重要(環境という教材について、教材研究が大切)であることが、岩立先生のお話の中に繰り返し出てきていました。そして、このことに加えて、子どもの育ち(何を経験しているのか)をとらえ、そのプロセスを記録として残していくことの大切さも、何度もお話に出てきていました。これらを踏まえて保育の実践を進め、自園の教育課程を見直すこと、さらに、教育課程を保護者や地域に開いていくことも大切であると話されました。その中で、教育課程は自園の保育(どのように子どもを育てていくのか)を具現化したものであり、保護者との契約書となるというお話に、ハッとしました。そう考えて、自園の教育課程を見直すことが必要だと強く感じました。
「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」については、5歳の終わり頃に出てくるであろう(出てきそうな)姿をまとめたものであるが、そうなるために、3歳では、4歳ではどのような保育をしていけばよいのかを考えることが大切であると話されていました。単純に、5歳の終わりにはこうなるのねで、終わるのではなく、そうなっていくためのそれ以前の保育(未満児を預かるのなら)の在り方をしっかり考えていく必要があると思いました。
カリキュラム・マネジメントをより確かなものにするためにということで、記録の重要性についても繰り返し、触れられていました。単に子どものしていることを記録として残すのではなく、何を経験しているのか、何が経験できていないのかを子どもの姿から見取り、経験(学び)を深めるには、あるいはまだ経験していないことを経験できるようにするにはどのような環境を構成したり、援助したりすることが必要なのかを考えて保育をした結果としての子どもの育ちのプロセスを、記録していこうと思います。また、子どもの姿や自身の保育について、短時間であっても園内で積極的に話題に出し、子どもの見方の視野を広げたり、教材研究を進めたりていくことも必要だと思いました。まずは、東京学芸大学附属幼稚園(小金井園舎)の記録のとリ方を参考にさせていただきます。東京学芸大学附属幼稚園(小金井園舎)の園内研修を例に挙げながら、改訂(改定)の背景や方向を踏まえた保育を実践していくためには、地道で丁寧な記録を取り、それを見直していくことで、新しい教育要領や保育指針に沿った保育となっているかを振り返ることが大切であり、有効なのではないかと強く思いました。
参加された方もそうでない方も、記録の取り方について、この機会にもう一度見直してみるとよいのではないでしょうか。ということで、感想を交えながらの今回の研修報告です。
次回は、平成31年1月19日(土)14:00~16:00
「困り感の共有と解決に向けて、保育を語り、質を向上させたり悩みを解決したりしよう」というテーマで、伊勢崎市立あかぼり幼稚園で開催します。
全幼研群馬支部研修部より
理事長より 度重なる自然災害にお見舞い申し上げます
度重なる自然災害にお見舞い申し上げます。
平成30年9月6日に起きました北海道地震に関しまして、被害のありました地域の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
震度7という、いまだかつて経験したことのない数字に驚きましたが、テレビ等の画面に映る光景に、なんといっていいかわからない心境です。
朝3時という時間でしたので、子どもたちが家庭にいたということには安堵しますが、地滑りに液状化、交通機関の断絶、電気や水道の供給ストップと、心配なことだらけです。一刻も早く回復することを願っています。
また、今週初めには大型台風が関西方面を直撃し、被害が大きくまだまだ通常の生活に戻っていない中での大地震に、渦中の皆様の不安や緊張、疲労を考えると何もできずにいることにもどかしさを感じております。
どうか皆様の園の関係者をはじめ家族の皆様が御無事でいらっしゃいますようにと祈るばかりです。
関係の皆様に、謹んで災害のお見舞い申し上げます。
平成30年9月7日
(社)全国幼児教育研究協会 理事長 福井 直美